インタビュー紹介
「地震後も住み続けられる家を」
30代子育て夫婦が意識を変えたのは
高知県香南市

子ども3人が思い思いに
長男の滉太朗君(6)がテーブルの下でポケモンカードを眺めるそばで、次男の慎之介君(4)がトランポリンで跳ねている。長女渚紗(なぎさ)ちゃん(1)はお昼寝中だ。
幼い3人を育てるのは、高知県香南市の田村寛之さん(35)、友里香さん(36)夫婦。以前は約10キロ西の高知市内に住んでいたが、5年前に木造2階建ての中古物件を購入して移り住んだ。高台に立つ自宅の居間からは約5キロ先の太平洋が見え、風も通る。「オーシャンビューでしょ」。寛之さんは冗談めかして言う。

津波の来ない場所を選んだのに
ゆかりのない場所に移り住んだのには訳がある。
「大前提だった」と夫婦が口をそろえるのが、南海トラフ巨大地震で津波に襲われないこと。以前住んでいたアパートは津波の浸水想定エリア内。戸建ての立つ高台は標高50メートル近いところにあることが決め手になった。
2011年の東日本大震災が意識を変えた。寛之さんは津波の映像をテレビで見て「同じ日本とは思えなかった」、友里香さんは「津波が来たら山に逃げなきゃと考えるようになった」と言う。
購入したのは1979年に建てられた旧耐震基準の家だ。購入の際にリフォームはしたが、住み始めた後、無料の耐震診断のチラシを見て試しに頼んでみると、結果は「倒壊する可能性が高い」。ショックだった。
「地震が起きたら子どもたちを守らなきゃいけないのに、緊急地震速報の音でパニックになったことがあって…」。友里香さんは安心して家で寝られないと強く感じたという。
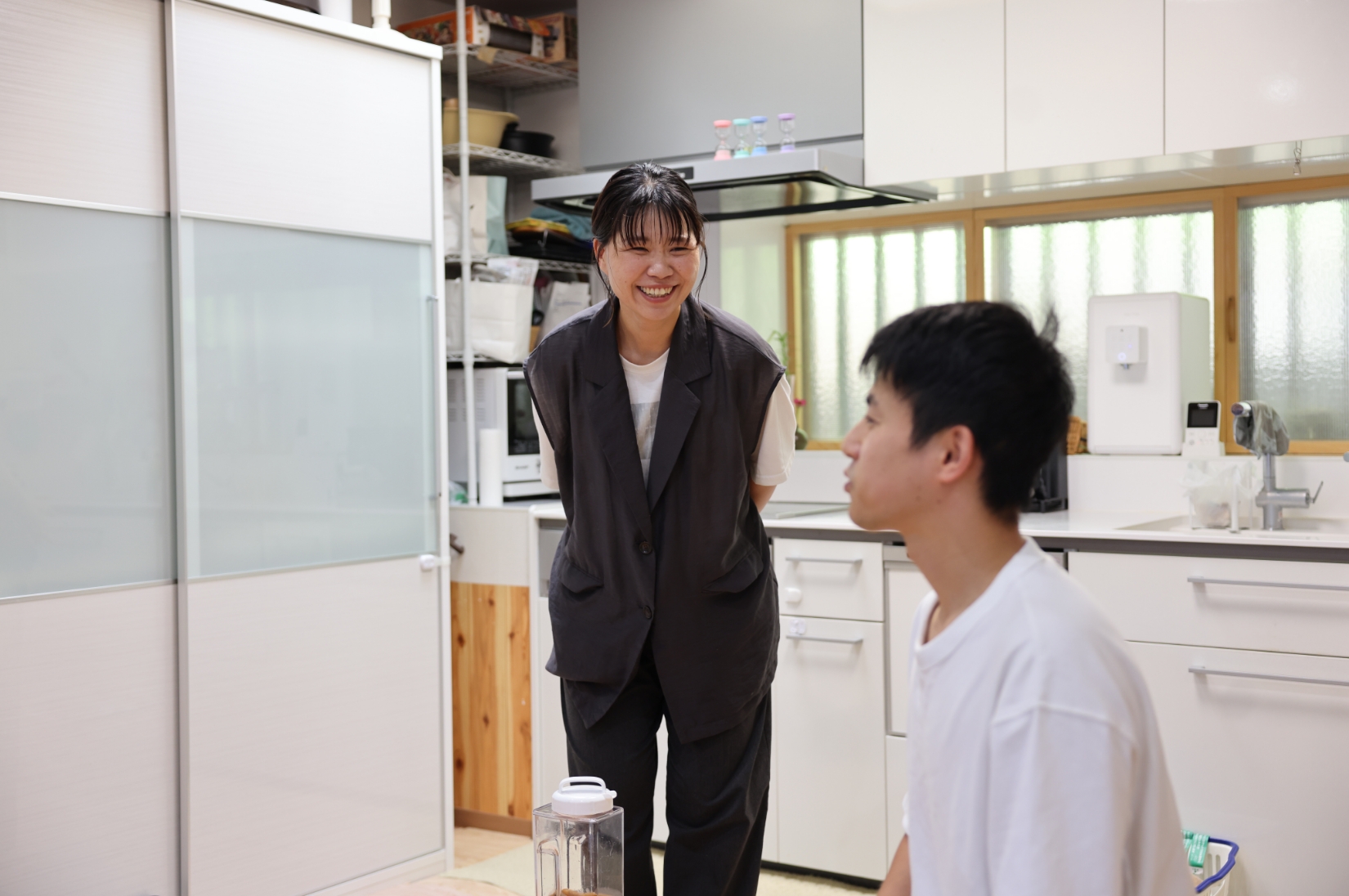
改修直前に南海トラフの臨時情報
業者が出した二つの補強プランでは満足できず、「震度7クラスの地震が来ても、住み続けられる家に」と求めた。2024年8月に南海トラフの臨時情報が出たのは、改修工事が始まるのを待っている時だった。
その2カ月後、台所の勝手口や風呂のドアをふさいで壁にするなど数十カ所を補強。かかった費用は総額約300万円(うち補助金165万円)だった。
ただ、おかげで「地震が落ち着くまで家におれる余裕ができました」と夫婦は言う。
最近は中古物件に関心を寄せる若い世代が増えている。寛之さんは「中古物件を買うのであれば耐震改修はマスト。すぐに地震が来て倒れたら、後悔する。やった方が良い、絶対に」
【取材にご協力いただいた皆様】
・田村寛之さん、友里香さんご家族
・株式会社アットホーム四国代表取締役、北村憲司さん
(※年齢や肩書などは2025年8月17日の取材時点のものです)
